開いてくれてありがとうございます!
えんでのブログを運営しているえんで です!
このブログ記事では、時代区分で学ぶ日本史講座と題して、時代ごとの大まかな流れを解説していこうと思います。
歴史を学ぶためにはまず流れをしっかりと学ぶことが大切です!
このブログ記事はこんな人におすすめ
・歴史を楽しく学びたい人
・教養を身に着けたい人
・一通りの歴史は知っておきたい人
※下記の大人の教養日本の歴史シリーズとは別シリーズなのでお気を付けください。
今日学ぶのはこの時代
旧石器時代を学びます!
旧石器→縄文→弥生→古墳→飛鳥→奈良→平安→鎌倉→南北朝→室町→戦国→安土桃山→江戸→明治→大正→昭和→平成→令和
という時代区分の最初に位置するのが、今回学ぶ旧石器時代。
つまり日本史の始まりとも言える大切な時代なのです。
この旧石器時代一言で表すなら、打製石器の時代です!
1.日本列島に人類がやってきた!
20万年前にアフリカで誕生した新人ホモ・サピエンスは、世界各地に広がっていきました。
そして、ついに日本列島にやってくる人類集団も現れました。
今から、約四万年ほど前だと言われてます。

「え?島国なのにどうやって日本に渡ってきたの??泳ぎ??」

「現在は島国だけれど、寒かった昔は海が凍ってて、日本列島は大陸とつながっていたんだよ。」
そうなんです。旧石器時代には日本列島は大陸とつながっていました。
ナウマン象やオオツノジカといった大型動物たちを追いかけながら、人類は日本列島にやってきたのです!
コラム 旧石器時代は幻の時代だった?!
ちょっとここで一休み。少し豆知識を紹介します。
今では日本でも存在が確認されている旧石器時代ですが、戦前は日本では存在しなかったとされてました。
しかし、戦後ある青年のおかげで旧石器時代は日本でもあったということが分かったのです。
その青年の名は、「相沢 忠洋」
納豆等を売りながら、考古学を学んでいた相沢さんは、群馬県の岩宿というところで、打製石器を発見!!
これがかの有名な岩宿遺跡です。
これはもう世紀の大発見です!!
なんてたって、今までないとされていた時代を発見したんですからね。
現代だと、
Twitterのプロフィール欄に、「新時代を発見した男」
なんてことが書けるわけです。
相沢さんは、日本の歴史研究に多大なる貢献をされた方なのです。
2、人類、石を砕く
冒頭で、旧石器時代を一言で表すなら、打製石器の時代だと言いました。
この打製石器、その名の通り、石を打ち砕いて作る石器です。
石を砕いて形を整え、ナイフにしたり、オノにしたり、はたまた槍にしたり。。
ほんと器用ですよね。
こういう話をするといつも思うのですが、誰が石同士を打てば、形を変えられるなんて発見したんでしょうかね。
私が旧石器時代に生きていれば、「石、硬い」
だけ思って、速攻猛獣に食べられていたことでしょう。
初めて打製石器を作った人類に、「なぜ作ろうと思われたのですか?」とインタビューしたいです。。
3、頻繁に引っ越す人類
旧石器時代の人々は頻繁に移動していました。
なぜならその当時、稲作などは始まっておらず、
その土地で食べ物がなくなればまた新たに食べ物を求めて別の場所に移動せざるを得なかったからです。
その当時、主食は肉や魚なので、無くなれば次の場所に移動していました。
頻繁に移動する日々は、色々な意味で刺激に満ち溢れていたことでしょう。
4、次回予告
ここまで読んでいただきありがとうございました。
旧石器時代、人類は石を砕いて石器を作っていました。
そして、次回人類は、石を磨くという技を習得します。
磨製石器の誕生です。
そして時代は縄文時代に。。
次回、縄文時代をとりあげます!!
参考文献
「私たちはどこから来たのか? 3万年前の航海再現で探る日本人の起源 」
閲覧日2020年8月17日
『詳説日本史研究』佐藤信 他著
2017年8月発行





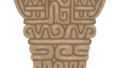
コメント