開いてくれてありがとうございます!
えんでのブログを運営しているえんで です!
このブログ記事では、時代区分で学ぶ日本史講座と題して、時代ごとの大まかな流れを解説していこうと思います。
歴史を学ぶためにはまず流れをしっかりと学ぶことが大切です!
※前回はこちら
前回の復習
前回は縄文時代について学びました。縄文時代は一言で表すなら「大きな気候変動の時代」です。
大きな気候変動によって、日本列島は大陸から切り離され、人々は生活の変化を余儀なくされました。
縄文時代の人々は、気候変動に対応する中で、縄文土器や弓矢などを作っていったのです。
しかし、一万年あまり続いたこの縄文時代も、ついに終わりを迎えます。そして時代は弥生時代に。。
今日学ぶのはこの時代。
弥生時代を学びます!
旧石器→縄文→弥生→古墳→飛鳥→奈良→平安→鎌倉→南北朝→室町→戦国→安土桃山→江戸→明治→大正→昭和→平成→令和
という時代区分の中で、三番目に位置するのが今回学ぶ弥生時代です。
弥生時代を一言で表すなら、「稲作の時代」です。
今や日本人の国民食である、「お米」。
その「お米」が日本列島にやってきたのが、弥生時代です。
縄文時代は、気候変動によって人類は生活を変えてきましたが、弥生時代は、「お米」によって生活が大幅に変わります。
では具体的に、「お米」によってどのような変化がもたらされたのか。その変化をみていきましょう
1、弥生人、本格的な農耕を覚える。
秋になると、

こんな風景を見る機会も増えます。テレビなどでみたことがある人もいるでしょう。
このように、田んぼに水を張って米を栽培することを、水稲耕作といいます。
この水稲耕作が始まったのが、弥生時代。
いよいよ本格的な農耕が始まったわけです。
米を作るという作業は、1日や2日でできるわけではありません。米作りは、春に田植えをし、夏は台風の被害を防ぎながら、やっと秋に収穫するという長い期間がかかります。
また、米作りは一人でできるものでもありません。皆の協力が必要です。
つまり、米作りは大人数でやる重労働。。
そんな米作りを行うために、弥生人はより大きな集落を作るようになります。
そうした証拠が今も、吉野ケ里遺跡等の遺跡となって残っているわけです。
2、私の長所は米作りが上手なところです。
弥生人は、大きな集落を形成するようになり、本格的な稲作を始めるようになりました。
そんな初めて稲作が始まったくらい、古い時代ではありますが、やはりいつの時代も人には得意不得意があるものです。
弥生時代にも、米作りが得意な人、苦手な人がいるわけです。
まだ、人類が今のように文明を発展させていなかった時代ですから、人類にとっても「子孫を残し、種を繁栄させる」という生物における第一目標がとても大切。

「僕、米作り苦手だけど、こうやって作れば良いんじゃないかな」

「いやいや、俺も苦手だけど、そうじゃなくてこうだろ」

「いや、私はこう思う」

「なんかよくわかんないや。。ま、いっか」
なんてのんきなことは生き残るためには言ってられません。
ですので、米作りがうまい人が中心となって、米作りを皆でしようという話になるわけです。
つまり、リーダーの誕生。
そうやって、弥生時代の人々は、リーダーという役職を生み出し、集落全体の運営を効率的に行っていきました。
※もちろんリーダーが選ばれる理由は、米作りの上手さだけではないでしょうから、
あくまで一例です。
3、弥生人、貯金をする
「米」というものは、肉や魚とは違いそう腐るものではありません。
つまり、余分にあったとしても、おいておくことができます。
また、「米」は、自分たちの手で栽培し収穫できるわけですから、生産量を決めることができるという特徴があります。
そのため、「米」という資産を弥生時代の人々は、貯蓄するようになりました。今でいう銀行口座に貯金するようなものです。
その現代でいう銀行口座の役割を果たしたのが、高床倉庫と呼ばれる建物です。

ここで豆知識を。。
高床倉庫はなぜ床が高いのでしょうか。
考えられている理由は2点あります。
一つは、ネズミなどの米を荒らす生き物が建物内に侵入するのを防ぐため。
もう一つは、地面との距離をとることにより、風通しを良くするため。
という2点です。
また、米の貯蓄用の道具はもう一つあって、それが弥生土器です。

縄文時代よりも土器は種類が増えました。
4、戦争の始まり
米の貯蓄を覚えた弥生人ですが、それにより悲劇も生み出されてしまいます。
米という資源を巡って、戦争が始まったのです。
人々は、戦争に勝つために、高いところに集落を作ったり(高地性集落)、集落を濠で囲ったり(環濠集落)したわけです。
また、日本列島に鉄器と青銅器がほぼ同時に伝わってきた事により、鉄器は武器として、青銅器は豊作や戦争勝利をお祈りする道具として使われるようになります。

※人類の資源利用法の歴史として、扱いが比較的簡単な青銅器を先に使えるようになり、
扱いが難しい鉄器はより技術が進歩した後の時代に使えるようになったと
言われています。
ですが、日本の場合、鉄器が発明された後に青銅器とセットで伝わったため、鉄器と
青銅器のほぼ明確な使い分けという現象が起こったわけです。
コラム〜文字のない時代の歴史がなぜわかるのか〜
21世紀を生きる私達が、遠い昔のことを知るすべが主に2つあります。
一つは、文字情報です。
例えば、中国では前王朝の歴史について現在の王朝がまとめるという慣習があるため、真実かどうかは別にしてもある程度、真実に近い歴史を知ることができます。
文字情報であれば、何年の◯月◯日に戦争が起きたなんていう細かいことは、その文字の読み方さえわかれば、知ることができるわけです。
ただ、文字情報で書いてあることがすべて正しいわけではないので、その解釈を巡って議論が起きますが、、
そして、もう1つは、文字情報以外の情報です。
文字情報以外の情報とは、遺跡や土器などの遺物のことです。
例えば、先程、弥生時代には戦争があったという話をしました。
弥生時代には文字がありませんから、歴史を知るすべが文字情報しかなかったら、戦争があったなんてわからないわけです。
ですが、明らかに武器によって殺された遺体が見つかっているため、弥生時代には戦争があったということが分かります。
このように、文字のない時代のことは、遺跡や遺物でしか分からないため、新発見があるたびにコロコロと歴史が変わるわけです。
「私たちの習ってきた歴史とは違う。これだから歴史は訳わからんくて面白くない」という気持ちも十分わかります。
ですが、習ってきた歴史とは違うということは、それだけ新たな事実がわかり、より真実に近づいているという証拠というわけです。
つまり、サスペンスのように、真実に主人公(今を生きる私達)が近づいていっている表れなのです。
5、次回予告
ここまで読んでいただきありがとうございます。
弥生時代は、「稲作の時代」でした。
「稲作」によって人類は生活を大幅に変更しました。
今まで、旧石器、縄文、弥生と三時代に渡って書いてきたわけですが、次回は箸休めとして
特集を組もうと思います。
その特集の題材は「邪馬台国」です。
「邪馬台国」といえば、所在地が
古代史最大の謎であり、ロマンあふれる話でもあります。
そんな「邪馬台国」について書いていこうと思います。
参考文献
『詳説日本史研究』佐藤信 他著 2017年8月発行



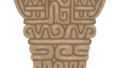

コメント